
葬儀を行う際、経済的な事情により通常の葬儀を行うことが難しい場合、「福祉葬(生活保護葬)」という制度を利用することができます。
この記事では、東京都で行う福祉葬について、申請手順・費用・注意点などを現役葬儀屋がわかりやすく解説します。
福祉葬とは?東京都で利用できる葬祭扶助の制度
福祉葬とは、生活保護を受給している方、またはそれに準ずる経済的困窮者のために、自治体が葬儀費用を一部または全額負担する制度です。
正式には「葬祭扶助(そうさいふじょ)」と呼ばれ、生活保護法第18条に基づいて実施されています。
各区市町村の福祉事務所が窓口となり、必要な審査を経て、葬儀屋に直接費用が支払われます。遺族に請求がいくことは基本的にありません。
この制度を利用することで、経済的に困窮している方でも「火葬だけの簡易な葬儀」を行うことができ、最低限の(尊厳のある)お別れが可能になります。
東京都で福祉葬を行う条件
福祉葬を利用できるのは、次のいずれかに該当する場合です。
- 故人が生活保護を受けていた
- 葬儀を行う親族も生活保護を受けている、またはそれに準ずる経済状況である
- 故人に身寄りがなく、引き取り手がいない
- 身元引受人がいても、葬儀を行うだけの資力がないと認められる
上記のいずれかに該当し、かつ福祉事務所の担当ケースワーカーが認めた場合にのみ、葬祭扶助(福祉葬)の対象となります。
東京都での福祉葬の方法と申請手順
東京都で福祉葬を行う場合、一般的には次のような流れになります。
逝去の連絡と福祉事務所への相談
まず、病院や施設で亡くなった場合、故人が生活保護受給者であれば、その情報をもとに福祉事務所へ連絡します。
受給していなかった場合でも、経済的に困難な事情がある場合は相談が可能です。
② ケースワーカーとの面談
担当のケースワーカーが、申請者(喪主予定者)の収入・資産・関係性などを確認します。
必要に応じて葬儀屋の見積書を提出します。
③ 見積書の提出と審査
葬儀屋から提出された見積書を基に、福祉事務所が葬祭扶助の可否を判断します。
事務所の承認が下りる前に葬儀を行うと、費用が支給されない場合があるため、注意してください。
④ 福祉葬の実施
承認後、指定の葬儀屋が葬儀を実施します。
福祉葬は通夜や告別式を行わず、火葬式のみ(直葬)が基本です。
なお、安置・納棺・火葬・収骨までの最低限の流れは含まれています。
⑤ 費用の支払い
葬儀後、葬儀屋が福祉事務所に請求を行い、費用は直接葬儀屋へ支払われます。
申請者や遺族に請求が届くことは基本的にありません。
東京都の福祉葬の費用と内容
東京都での葬祭扶助の支給額は12歳以上はおおむね20万円前後、12歳以下は16万前後が目安です。
実際の金額は自治体によって多少異なりますが、以下の内容が一般的です。
- ご遺体の安置(1~2日程度)
- 納棺作業・棺・仏衣
- 霊柩車での搬送
- 火葬料金
- 骨壺・収骨容器
逆に、以下のような費用は含まれません。
- 通夜・告別式などの儀式
- 会葬者の飲食接待費
- お布施(宗教者への謝礼)
- お供物・生花などの装飾
あくまで「最低限の葬送」を目的とした制度である点を理解しておきましょう。
東京都で福祉葬を取り扱う葬儀屋の選び方
福祉葬を依頼できる葬儀屋は、葬祭扶助の取り扱い実績がある業者を選ぶことが重要です。
福祉事務所との連携がスムーズで、必要書類の手続きにも慣れています。
筆者の会社も何度か福祉葬を担当したことがありますが、正直言うと手続きがかなり複雑です。
そのため福祉葬を検討している方は、依頼したい葬儀屋に事前に問い合わせることをおすすめします。
葬儀屋選びのポイント
- 「福祉葬」に対応しているかを確認
- 福祉事務所への提出書類(見積書など)を代行してくれるか
- 火葬場や安置施設までの距離が近いか
- 対応が丁寧で、急な逝去時も相談に乗ってくれるか
特に東京都では、桐ヶ谷斎場・町屋斎場・堀ノ内斎場など主要な火葬場と提携している葬儀屋を選ぶと、移動費用も抑えられます。
福祉葬の注意点
福祉葬の申請や実施には、いくつかの注意点があります。
- 葬儀を行う前に必ず福祉事務所の承認を受ける
- 他の親族が費用を負担できる場合、対象外になる可能性がある
- 故人の遺産がある場合、支給対象にならないことがある
- 火葬後の遺骨の引き取りも、原則申請者が行う必要がある
また、福祉葬は「無料葬儀」と誤解されがちですが、あくまで行政が定めた範囲内での補助である点に注意が必要です。
申請者が希望する内容によっては、福祉葬の申請が通らないケースもあります(葬儀屋の見積もりで通夜や一日葬を選択していたり、費用が高額な場合など)。
ここだけの話ですが、自治体によって福祉葬の申請の通りやすさは異なります。
筆者の会社で実際にあったケースで、福祉葬で生前相談を行い見積もりまで準備していたにも関わらず、申請が却下された方がいました。
ケースワーカーと話をしているうちに式をやってあげたいという思いが強くなったようで、対象者の危篤の報せを聞いて集まった親族たちから葬儀費用を募ろうと考えたようです。
しかし結局葬儀費用を集めることができないまま対象者が亡くなり、自費で葬儀を行うことになり、見積もり時よりもさらに内容を絞った直葬になってしまいました。
経済的に困窮していることは何も恥ずべきことではありません。
そういった方のために制度が存在するので、自分だけの力で何とかしようとせず、ケースワーカーに素直に打ち明けましょう。
東京都で福祉葬を検討する際の相談窓口
東京都内で福祉葬を検討している場合、以下の窓口に相談するのが一般的です。
- お住まいの区市町村の福祉事務所
(例:新宿区福祉事務所、世田谷区生活福祉課など) - 葬祭扶助の取り扱い経験がある葬儀屋
- 地域包括支援センター(高齢者の支援窓口)
緊急の場合は、葬儀屋が代行して申請手続きを行うこともあります。
葬儀屋によっては、24時間体制での相談窓口を設けているところもあります。
まとめ:東京都での福祉葬の方法を正しく理解して安心の葬儀を
東京都の福祉葬(葬祭扶助)は、経済的に葬儀を行うのが難しい方にとって、非常に心強い制度です。申請の流れを正しく理解し、信頼できる葬儀屋と福祉事務所に早めに相談することで、スムーズに手続きを進められます。
ポイントをまとめると次の通りです。
- 福祉葬は生活保護法に基づく制度で、自治体が葬儀費用を負担
- 東京都では12歳以上はおおむね20万円前後、12歳以下は16万前後が目安
- 申請は必ず葬儀前に行う
- 火葬式のみのシンプルな形式が基本
- 福祉事務所と連携できる葬儀屋を選ぶことが大切
「経済的な事情で葬儀ができない」と感じたときは、迷わずまず福祉事務所へ相談してみてください。
制度を正しく使えば、誰もが尊厳のある最期を迎えることができます。

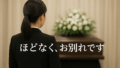

コメント