
葬儀の現場に携わっていると、よくお客様からこんな質問をいただきます。 「互助会と葬儀保険って、どっちに入るのがいいんですか?」 どちらも「将来の葬儀費用を準備する仕組み」ですが、 葬儀屋の立場から見ると、 この記事では、現場で見てきたリアルな事例を交えながら、 互助会とは、冠婚葬祭を行う会社(葬儀屋グループなど)が運営する前払い式の積立制度です。 私たち葬儀屋の現場では、 早い段階から準備できる安心感 物価上昇の影響を受けにくい 会員特典が豊富 互助会の移籍とは 提携している互助会会社間に限りますが、他県への引っ越しなど、加入していた互助会会社の対応エリアから離れた場合に、引っ越し先の別の互助会会社に契約内容を移して互助会を利用すること。 契約内容によっては、希望の移籍先に必ず移籍できるわけではないため、注意が必要です。 葬儀保険(終活保険・葬祭保険とも呼ばれます)は、 つまり、互助会が「サービスの前払い」なのに対し、 葬儀の打合せで、「互助会に入っていたのに、思っていたより費用がかかった」という声をよく聞きます。 ただし、どちらにも一長一短があります。 葬儀屋の立場から言えるのは、 「仕組みを理解して、自分に合った備え方を選ぶこと」 実際の現場では、互助会+葬儀保険の併用という方も増えています。 互助会 → 基本的な式場・祭壇を確保 葬儀保険 → 料理・返礼品・僧侶謝礼などをカバー こうすることで、「現場の手配+現金の備え」が両立できます。 最後に、葬儀屋スタッフとしてお伝えしたいのは、 実際、筆者の会社でも、 「本人が互助会に入っていたのに、家族が知らず別の葬儀屋で葬儀をしてしまった」 「保険証券が見つからず、保険金を請求できなかった」 加入したら、「契約内容を家族に共有する」ことも、立派な“終活”の一部です。 葬儀の準備というと、「縁起でもない」と感じる方も多いですが、 互助会も、葬儀保険も、目的は同じ、 それぞれの違いを理解し、ご自身やご家族に合った方法を選ぶことで、
実はまったく性質の違う制度です。
「仕組みを理解しないまま契約して後悔される方」も少なくありません。
互助会と葬儀保険の違い・メリット・注意点を、葬儀屋目線で解説していきます。
現場で感じる「互助会」の実態
互助会とは?
会員は月々一定額(例:1,000〜3,000円程度)を積み立てていき、将来的にその葬儀屋の葬儀サービスを割安で利用できるという仕組みです。
「互助会に入っておいたから安心」というお客様に多く出会います。
確かに、互助会にはメリットも大きいです。葬儀屋目線で見る 互助会のメリット
互助会は月々の積立制なので、若い頃から無理なく始められます。
お金を預けておくことで、「将来の不安が減った」と話される方も多いです。
契約時の金額でサービスが確定しているため、
葬儀費用が値上がりしてもプラン料金は変わりません。
会館の使用料割引、供花や返礼品の特別価格など、
地元の葬儀屋ならではの特典が受けられます。
現場で感じる 互助会の注意点
ここがよく誤解される部分です。
積立金は「基本プラン(祭壇や式場使用料など)」にあてられるもので、
料理・返礼品・お布施・供花などは別途費用がかかります。
結果的に、総額では追加費用が数十万円になることも。
互助会は「その会社のサービス利用権」なので、別の葬儀屋では原則利用できません(互助会の移籍という制度はあり)。
実際、転勤や引越しで他県に移られた方が「互助会の権利が使えなくなった」と相談に来られることもあります。
解約は可能ですが、会社によって手数料があり、
返金が積立額の6〜7割程度になるケースも。
「使わないともったいない」と感じて続けている方も少なくありません。
一方の「葬儀保険」はどう違うのか?
葬儀保険とは?
保険会社が提供する少額死亡保険です。
被保険者が亡くなった際に、保険金(例:30万〜300万円程度)が現金で支払われます。
葬儀保険は「お金の備え」です。
【葬儀屋目線で見る 葬儀保険のメリット】
葬儀保険の保険金は現金で支払われるため、
どの葬儀屋を利用しても構いません。
家族が自由に業者を選べる点は非常に大きな利点です。
葬儀費用だけでなく、納骨費用・法要・仏壇購入などにも利用可能。
「喪主になったご家族の手元資金」として助かる場面が多いです。
持病があっても入れる「告知なしタイプ」などもあり、
高齢者でも備えられます。
【現場で感じる 葬儀保険の注意点】
解約しても保険料が戻らないタイプが多く、
「積立」とは違うことを理解しておく必要があります。
月々1,000円でも、20年加入すれば総額24万円。
保険金が30万円ならトータルではほぼトントンです。
加入後すぐは「病気死亡は対象外」など、
条件付き期間が設定されていることがあります。
互助会と葬儀保険の違いまとめ
項目
互助会
葬儀保険
仕組み
葬儀サービスの前払い積立
保険金を現金で受け取る
契約先
葬儀屋・互助会会社
保険会社
お金の使い道
指定葬儀屋のサービス限定
自由(葬儀・法要・納骨など)
利用開始時期
積立完了後
契約後すぐ(待機期間あり)
解約
可(手数料あり)
可(掛け捨て型は返金なし)
自由度
低い(指定葬儀屋のみ)
高い(どの葬儀屋でもOK)
向いている人
信頼できる葬儀屋が決まっている
柔軟に備えたい、比較したい人
現場で見た「後悔しない備え方」
逆に、「保険に入っていて現金がすぐ下りたので助かった」という方も多いです。
それが一番の安心につながります。
併用するお客様も増えています
たとえば:
特に、家族葬や直葬を選ぶ方が多い今の時代には、
柔軟に対応できる備え方として人気です。
葬儀屋スタッフからのアドバイス
「どんな備え方を選んでも、必ず“見える形”で家族に伝えておくこと」です。
というケースが本当に多いです。
まとめ:どちらが正解ではなく、「自分に合う備え方」を選ぶ
タイプ
向いている人
特徴
互助会
葬儀屋が決まっている人
サービスを前払い。特典あり。
葬儀保険
柔軟に備えたい人
現金で自由に使える。
併用型
バランスよく備えたい人
基本+追加費用を両立できる。
最後に(葬儀屋としての想い)
現場で数多くのご葬儀をお手伝いしてきた私たちは、
「事前の備えこそ、家族への思いやり」だと感じています。
「大切な人を安心して送り出すための準備」です。
“その時”に慌てない、心の余裕を持てるはずです。



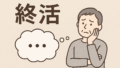
コメント