
葬儀に参列したとき、または喪主として式を執り行う際、
「この言葉ってどういう意味?」と思った経験はありませんか?
葬儀では、日常生活ではあまり聞きなれない「専門用語」が数多く登場します。
意味を知らないままでは、葬儀屋との打ち合わせや読経中の説明も理解しづらく、不安を感じる方も少なくありません。
本記事では、葬儀屋勤務の筆者の実体験をもとに、あ行〜な行までの主要な葬儀用語を分かりやすく解説します。
知っておくと葬儀の理解が深まり、安心して儀式に臨めるようになります。
葬儀用語を知る意義
葬儀の専門用語は、仏教・神道・キリスト教など宗教的背景や、日本独自の風習から生まれています。
言葉の意味を理解することは、単なる知識ではなく、故人をより深く敬い、正しく見送るための準備です。
| 理解しておくメリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| 意味を知ることで慌てない | 打ち合わせや式中の案内に冷静に対応できる |
| 儀式の意図を理解できる | 各所作に込められた意味を感じ取れる |
| 正しいマナーを身につけられる | 宗派・慣習の違いにも柔軟に対応可能 |
あ行の葬儀用語
後飾り(あとかざり)
火葬後に自宅でお骨を安置するための簡易祭壇。
多くはダンボール製で、白布をかけて花や位牌を飾ります。宗派により形式が異なります。
一周忌(いっしゅうき)
亡くなってから一年後に行う法要のこと。
神道では「一年祭(いちねんさい)」と呼ばれます。
位牌(いはい)
故人を祀るための木の板。戒名・俗名・没年月日を記します。
葬儀直後は白木位牌を使い、四十九日後に「本位牌」へ。
院号(いんごう)
戒名の最上部につく称号「〇〇院」の部分。
生前の功績や信仰心に応じて授けられます。
引導(いんどう)
僧侶が棺の前で法語を唱え、故人を浄土へ導く儀式。
「引導を渡す」という言葉の語源でもあります。
宇宙葬(うちゅうそう)
遺灰をロケットで宇宙空間に打ち上げる新しい供養の形。
費用は50万〜100万円以上で、まだ取り扱い業者は少数。
永代供養(えいたいくよう)
お墓の後継者がいない場合、寺院や霊園が永続的に管理・供養を行う仕組み。
核家族化により利用者が増加中。
か行の葬儀用語
改葬(かいそう)
お墓を別の場所へ移すこと。自治体で許可証の手続きが必要。
墓じまいの一環として増加傾向にある。
戒名(かいみょう)
仏の世界での新しい名前。宗派により「法名」「法号」と呼ぶ。
位により費用は数万円〜100万円超。
火葬(かそう)
遺体を焼き骨にする行為。「荼毘に付す」とも言う。
日本では火葬率99%。
火葬許可証
死亡届提出後に発行される許可証。火葬後は「埋葬許可証」に切り替わる。
紛失に注意。
カロート
墓石の下にある遺骨を納める空間。
地下型・丘型が存在する。
供花(きょうか)
葬儀で供える生花。
金額統一でトラブル回避するのがおすすめ。
享年/行年
前者=数え年、後者=満年齢。
表記は宗派・地域により異なる。
グリーフケア
遺族の悲しみを支援する心理的ケア。
カウンセラー資格制度も存在する。
互助会
冠婚葬祭の積立制度。毎月の掛金で割安サービスを受けられる。
さ行の葬儀用語
散骨(さんこつ)
ご遺骨を粉末化し、海や山などに撒く自然葬の一種。
海洋散骨・樹木葬・宇宙散骨など多様化しています。
社葬(しゃそう)
企業が主催する葬儀。社長・役員・功労者が対象。
規模が大きく、数百名規模の参列になることもあります。
宗旨・宗派(しゅうし・しゅうは)
-
宗旨:宗教そのもの(例:仏教、キリスト教)
-
宗派:宗旨の中の細分化(例:浄土真宗、日蓮宗など)
樹木葬(じゅもくそう)
墓石の代わりに樹木を植えて供養する方法。
「自然に還る」思想から人気が高まっています。
施主(せしゅ)
葬儀費用を負担する人。喪主と異なる場合もあり。
例:喪主=長男、施主=親族代表など。
た行の葬儀用語
玉串奉奠(たまぐしほうてん)
神道の儀式。榊の枝を神前に捧げ、拝礼する。
仏式での「焼香」にあたる。
通夜(つや)
葬儀前夜に行う儀式。故人を囲み最後の夜を過ごす。
通夜で食べる料理は「通夜振る舞い(つやぶるまい)」
塔婆(とうば)
故人供養のため墓に立てる木の板。五輪塔の形。
卒塔婆と表記する場合もある。
弔い上げ(とむらいあげ)
最後の法要を意味し、以後の法事を終える区切り。
三十三回忌・五十回忌が一般的。
友引(ともびき)
「友を引く」との俗信で葬儀を避ける日。
元々の意味は「勝負の決着がつかない」「共に引き分ける」。
火葬場が休業の場合が多いが、全国の火葬場が休業するわけではないので、実は葬儀をしようと思えばできる(かなり珍しがられますが)。
な行の葬儀用語
直会(なおらい)
神道の儀式の一つで、神への供物を下げて共に食べる行事。
神と人が一体となる意義を持つ。
新盆(にいぼん/しんぼん/あらぼん)
故人が亡くなって初めて迎えるお盆。
四十九日より前にお盆が来る場合は、翌年に行うのが一般的です。
納棺(のうかん)
故人を柩(ひつぎ)に納めること。
納棺師が遺体を清め、死装束を整えます。副葬品も一緒に納めることが可能。
納骨堂(のうこつどう)
遺骨を保管・安置するための施設。
短期預かりから永代供養付きまでタイプは様々です。
野辺送り(のべおくり)
葬列を組んで柩を墓地へ運ぶ伝統的風習。
現在では霊柩車による出棺が主流。
祝詞(のりと)
神道における祈りの言葉。
言霊の力を持つとされ、祭事で神前にて唱えます。
まとめ|葬儀の言葉を知ることは「心の準備」になる
葬儀の専門用語は一見難しく感じますが、意味を知ることで葬儀の流れや宗教的背景が理解しやすくなります。
喪主・参列者・遺族、どの立場でも「知っておくことで安心できる知識」です。
いざというときに焦らず対応できるよう、
この記事を「葬儀用語辞典」としてブックマークしておくと安心です。
次回の記事はこちら
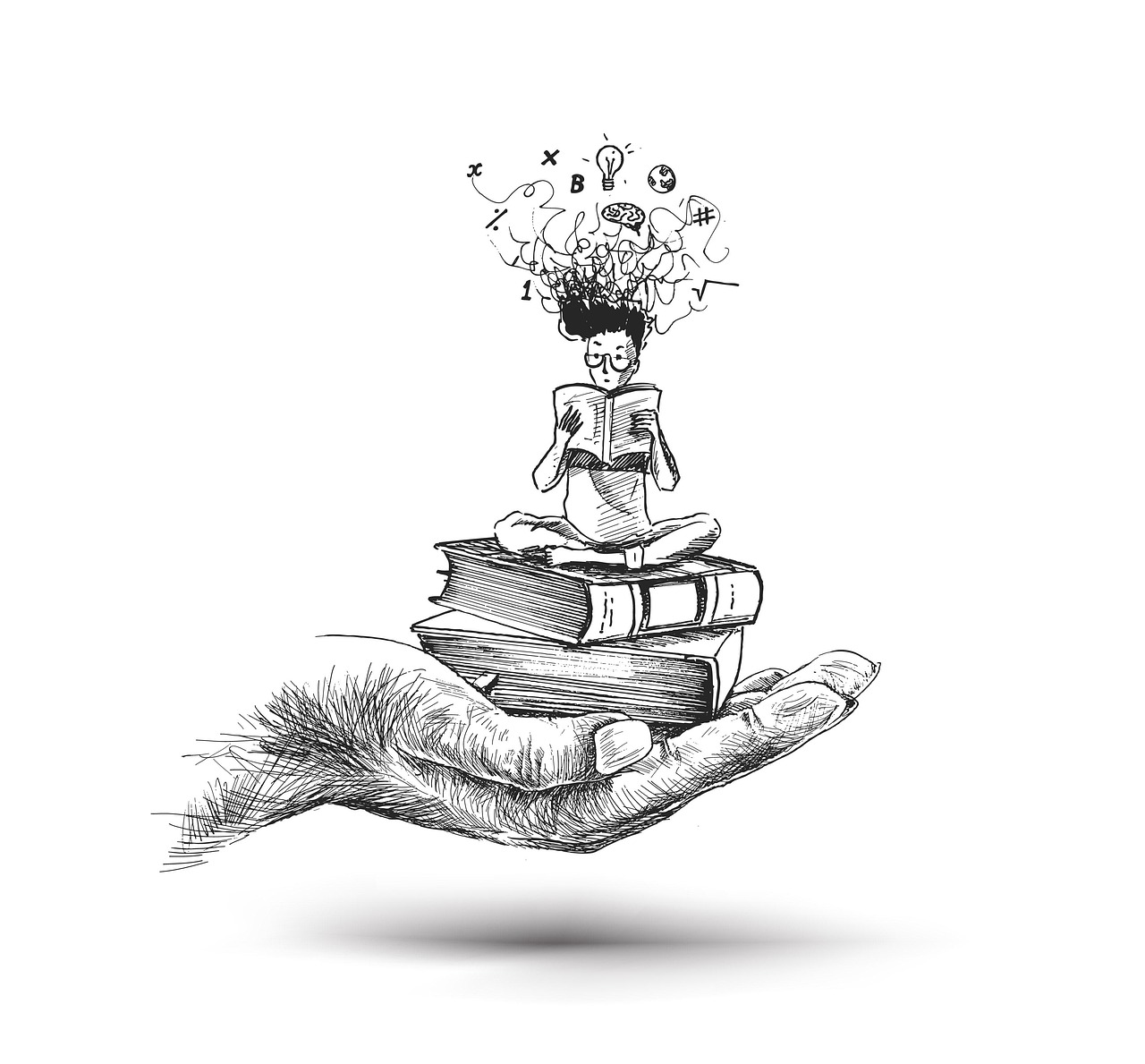







コメント